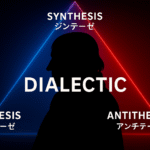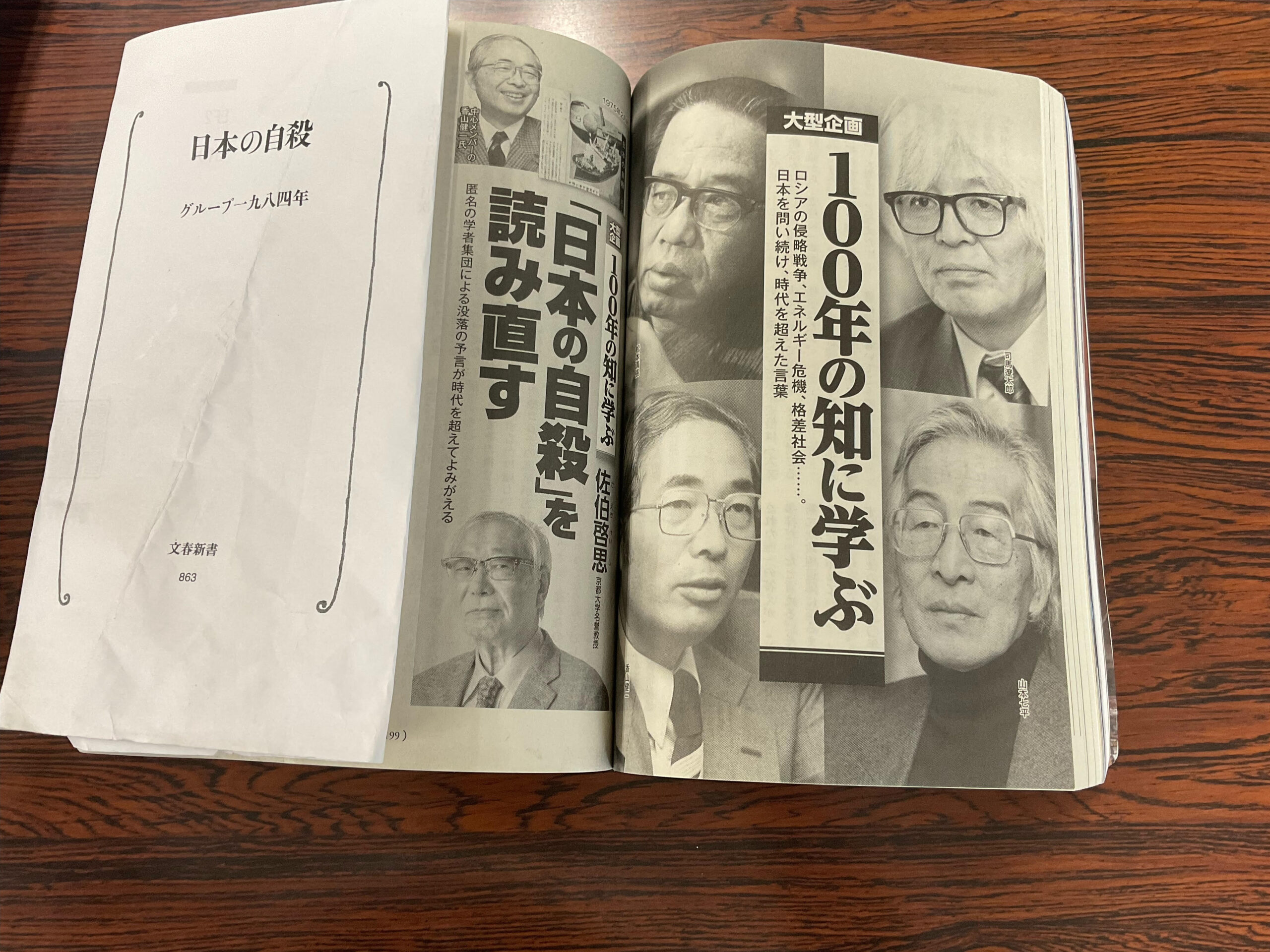
―祇園精舎の鐘の声,諸行無常の響きあり―
1 前号での予告
前号では,次号(今号のこと)では最近の月刊「文藝春秋」に載せられたある論考を基に持論を述べたいと締めくくった。
今年の正月のまだ松の内のある日,知り合いの「週刊文春」のT記者が新年の挨拶にと私の事務所をひょっこり訪ねてきてくれた(ちなみに私の今の事務所は文藝春秋のすぐ目の前にある。)。
そのとき彼が“手土産”代わりにと持ってきてくれたのが月刊「文藝春秋」の(今年の)新年号であった。それは「創刊100周年・新年特大号」と銘打ち,「大型企画・100年の知に学ぶ」として何人かの知識人の論考を載せていた。
パラパラとめくってすぐ目にとまったのが,佐伯啓思・京都大学名誉教授の「『日本の自殺』を読み直す」という論考だった。読み進むうちに,私は大変な共感を覚え,いささか興奮した。それが,今日の“日本の危機”は「文明論の欠如」によるものと,ずばり指摘するものだったからである。
2 月刊「文藝春秋」1975年2月特別号に掲載された「日本の自殺」と題する論考
日本の高度成長がそろそろ終焉を迎えつつあるかに見えた1975年(昭和50年),その年の「文藝春秋」2月特別号に「日本の自殺」と題する論考が掲載された。著者名は「グループ1984年」とされ,匿名の学者集団により執筆されたとの体を装ってはいるが,その論考の後掲・文春新書版(2012年)に寄せられた関係者の“証言”(?)によれば,著者は当時の日本の保守の最大の論客香山健一氏による単独執筆であったと推察される。
いうまでもなく,この「グループ1984年」というのは,イギリスの作家ジョージ・オーウェルが1949年に刊行した近未来小説「1984(年)」をもじったものである。これはその刊行から35年後の世界のある国(地域)がその姿さえ見せぬ“偉大な兄弟”によって統治・支配される独裁国家・監視国家になっているというものである。私は,中学生のころ,今は亡き長兄が我が家(私の実家)の書斎にこの本を置いていたのをたまたま手にし,当時の私にはいささか難解な本ではあったが,読み進むうちに大変な息苦しさと恐怖心を覚えたのを記憶している。特に主人公が愛し合った女性と隠れ家で暮らすある場面で,“振り返ったらその女性が化粧をしていた”という場面だけは何故か今でも鮮烈に覚えている。それがオーウェルの描く近未来の独裁国家・監視国家を象徴するエピソードのように思えたからである。
習近平氏の中国が新疆ウイグル自治区で現に展開している恐るべきまでに徹底した監視社会の実情を知るとき,オーウェルが「1984年」で描いてみせた近未来の社会の恐怖がたんなる絵空事ではないのではという戦慄を覚える。
ちなみに,数年前の日本のある新聞に寄せられたインドのある経済人(エコノミスト)(ひょっとして学者だったかもしれない)の論考が,「今や資本主義の発展にとって民主主義(制度)は必ずしも有用でもなければ必然でもない。独裁体制の方が資本主義の発展にとってより優れている。」という趣旨のことを述べていたのをみて衝撃を受けたのを覚えている。おそらくこれは,中国や今はやりの“グローバルサウス”の一定の国の経済伸長を思い描いたものであったろう。経済発展の競争において民主主義国家が全体主義の独裁国家に敗れる―ジョージ・オーウェルの描いた「1984年」の近未来社会の恐怖は,そのときにわかに現実味をおびたものになる。
3 「日本の自殺」が描いたもの
1975年に発表された「日本の自殺」は,その後2012年(平成24年)に「文藝春秋」3月号に再録され,更に同年5月文春新書「日本の自殺」として刊行されたという。
佐伯教授の冒頭の論考に触発された私は,とりあえずこの文春新書版をアマゾンの中古市場で求めようとしたがびっくりするほどの高値であったので諦め,国会図書館でこれを借りることとした。
「神々の終焉」(拙著。南雲堂。1993年)という問題意識を持つ私は,「グループ1984年」の正体が何であれ,早や1975年という時代において「日本の没落」を予言するなど“只者”ではないと,大いなる期待をもってこの本を手にした。そして何度も何度も読み返した。佐伯教授の前掲論考に触発され,刺激された私にとって,最初の読後感は,正直なところ期待通りでもあり,期待はずれでもあった。しかし,何度も読み返すうち,最初に感じた“違和感”は次第に薄れていき,この論考の“真髄”とするところに,私の思いは収斂されていった。
私が無条件に賛同するのは,この本の冒頭に述べられた
「過去6000年間におけるこの21の文明の『種』の栄枯盛衰の歴史のドラマとその比較研究は,文明の発生,成長,挫折,解体の原因やその一般的パターンについて,われわれになんらかの示唆を与えてくれるものなのであろうか。」
という基本的視座である。
拙著「神々の終焉」(南雲堂)で書いたように,西洋の最後の“神”であるマルクス主義の終焉を自覚し,我々人類を今日支配する西洋文明(西欧文明ではない!)の“行く末”を見定めるためには,そのよって来たるところ(淵源)を確かめるしかない―として,私は1988年(昭和63年)より今は亡き妻とともに中東・アラブ世界歴訪の旅に出た。それは文明の“始まり”を知ることによって,その文明の“終わり”を予測・予知し得るという視点であった。
そして,「日本の自殺」が同じくその冒頭において
「文明の発生,成長,没落という歴史の長期波動のなかで,なぜわれわれが特に没落の過程に焦点を絞ることになったのか」
といみじくも指摘する点こそ,地球人類が繁栄を極めたかに見える「西洋文明」が今やその「終焉」(神々の終焉)を迎えんとしているという私自身の危機意識とぴたりと符合する。
また,「日本の自殺」が
「まさに巨大化した世界国家がその心臓部の繁栄をもたらし,そして実に皮肉なことに,この繁栄こそがめぐりめぐってやがては,世界国家の心臓部を衰弱させることになっているのである。この意味では,没落は繁栄の代償であり,滅亡は巨大化の代償であったのだ。」
と鋭く指摘する点こそ問題の核心を衝いているのであり,両手を挙げて賛同する。
もちろん,この論考で考察の対象とされているのは,戦後の高度成長を経て“世界の経済大国”となった1975年当時の日本である。ただ,繁栄の頂点に達したとき没落が準備されているという命題は普遍的な法則であるといってよい。いずれこのスサノオ通信でも近いうちに「グローバルサウスとは何か」というテーマで触れることとするが,この法則は“失われた30年”に苦しむ日本だけではなく,“パクス・アメリカーナ”に表現されたような覇権国家アメリカという“大国の興亡”にこそ最もよくあてはまるように思われる。
それはさておき,「日本の自殺」は,1975年当時の日本が
「日本は軍事力によらずまた軍事力を持たない歴史上極めて特殊な非軍事経済大国として巨大な経済的勢力圏を持つ世界国家を作り上げ」
て「繁栄の頂点」に立ったが故に,まさにそのとき「日本経済没落」のさまざまな「兆候」を見せはじめていると指摘する。
著者は,この「没落の兆候」を古代ローマ(パクス・ロマーナ)の繁栄と衰退,滅亡になぞらえ
「世界国家の心臓部の繁栄→豊かさの代償としての放縦と堕落→共同体の崩壊と大衆社会化状況の出現→『パンとサーカス』という『シビルミニマム』→増大する福祉コストとインフレとローマ市民の活力の喪失→エゴと悪平等主義の氾濫→社会解体というプロセス」
の中に位置付けることが出来るという。
ローマの繁栄と没落が一般によくいわれるように「パンとサーカス」に象徴されるものかどうか,私は的確に論評する能力を持たない。また,「日本の自殺」の著者が「パンとサーカス」になぞらえて,没落の兆候と指摘する当時の日本の様々な具体的事象が,“例として”はたして適切なものかどうか,首を傾げたくなるようなものも含まれている。
たとえば,
「公害防止の大義名分のもとに長期的,総合的配慮を欠いた厳しい規制のごり押しを続ける」
と疑問を投げかけるくだりや,
「国鉄職場の荒廃ぶり」(国労,動労のことであろうか。)
を嘆くあたり,また
「福祉はともすると自律の精神を人間から喪失させ,全てを他人や国家に依存して生きようとする遊民を大量発生させ,かれらの魂を蝕んでいく危険を持っている」(美濃部都政批判であろうか。)
とまで言い切るあたりは,いささか苦笑を禁じ得ない。
しかし,このような指摘も,当時日本の保守の論客の第一人者のひとりと目されていた「日本の自殺」の著者(香山健一氏)が,世の中に向って自らの主張の“説得力”を根拠づける具体例としてこのようなことを挙げた(というより挙げざるを得なかった)という“時代の制約”を考えれば,今となってこれをあれこれ批判してみても生産的ではない。
あくまで問題の核心は,著者が挙げる「日本の没落の兆候の具体例」の適否にあるのではなく,当の著者自身が言うように,
「この状況の中では,『保守か革新か』などという古い色分けは全くなんの歴史的意味を持ちえないし,『体制か反体制か』『福祉国家か社会主義か』などという分類も完全に時代遅れで陳腐なものと化す。真のイシューはこうした古めかしい,低次元の発想を遥かに超えたところにしか存在しないのである。それは文明の転換と再生への飛躍の問題であり,それなしに現代文明は没落を回避することはできないのだ。」
という点にこそある。
そして,「日本の自殺」が次のように言う点は,今日においてなお色褪せるどころか,益々現実味を帯びてきているといってよい。
「豊かさも便利さも,そして情報化,都市化,大衆化,平和化,福祉,自由,民主主義,近代化も,現代文明が高く掲げてきたプラスの諸価値を含んでいた。これらのプラスの諸価値の実現のために,20世紀文明はまっしぐらに進んできたといってもよいであろう。だが,およそ人間社会の出来事になんらのマイナスを伴わない絶対的プラスというものは存在しない。節度を越え,調和を喪失したとき,プラスの価値の一途の追及の動きはある臨界点を越えて突如として符号を変えてしまうのである。人々はこのことを今日,資源問題や公害問題を通じてようやく少しずつ理解しつつある。」
そして,「日本の自殺」は,「豊かさの代償」として,次の3つを挙げる。
「資源の枯渇と環境破壊という代償」
「使い捨て的な大量生産,大量消費の生活様式(正しくは,生産様式であり,かつ生活様式であるというべきか―錦織―)が人間に与える悪影響,資源の浪費,廃棄物の増大による環境破壊」
「便利さの代償として,日本の青少年の体力や知力の低下」
いずれも極めて今日的な問題として,おおかたの異論をみないところであろう。
もっとも,第3の点は異論があるかもしれない。しかし,現代日本において「知性の劣化」が恐ろしいまでの勢いで進行し,現代日本を内部から蝕んでいる―しかも,それは青少年どころか日本の社会の各界各層の中堅どころにおいて広汎に進行している,深く静かに潜行している―という強い危機感を抱く私(もやは“絶望感”に近いものがある)にとっては,全く異論のないところである。
その意味で,「日本の自殺」が,
「現代人のあいだに見受けられる恐るべき知力の低下,倫理能力の喪失,判断力の全般的衰弱の秘密が,いまこそ本格的に解明されなければならないであろう。」
とする点は,余りにも鋭くかつ本質的な指摘として無条件に賛意を表する。
また,「日本の自殺」がかかる事象を「情報化の代償」として捉えている点は,それが「マスコミの発達と教育の普及」にあるとする点は当時の“時代の制約”によるやむを得ないものとしてさておき,IT技術の高度化に伴う現代世界や日本の“情報化時代の到来と,それが反面においてもたらす危機的状況の深化”がいかに人類社会に不幸を与えているかを嫌というほど自覚している我々は,その慧眼にひたすら敬意を表するしかない。
4 「日本の自殺」の時代的背景と歴史的制約
さて,この「日本の自殺」の著者は,何故にこの論考に「日本の自殺」というタイトルをつけたのであろうか。
それは次のくだりに明解に語られている。
「日本の没落の危険は資源問題や輸出市場などの客観的,外部的,物質的制約条件のなかに存するのではなく,日本社会の内部的,主体的,精神的,社会的条件のなかにこそひそんでいるのである。」
「危機は実は資源の制約,環境の制約などのなかにあるのではなくて,日本人の魂と社会制約の深部にこそあるのである。」
「このような日本社会の内部崩壊によるカタストロフの可能性」
これが「日本の自殺」の意味である。日本は,「パンとサーカス」に溺れた古代ローマ帝国と同じように,堕落した大衆社会へと転落することにより“自死”するというわけである。
ここまで来ると,いささか抵抗を感ずる人が多いであろう。現代日本の危機は地球規模で起きている「文明的危機」(神々の終焉)と同質のものである。それは,人類が直面する3つの危機(環境・資源,核兵器,南北問題―拙著「神々の終焉」参照。)という優れて客観的,外部的,物質的諸条件の問題である。そして,この危機の本質を理解せず,あいかわらず「科学技術を万能の神と仰ぎ」,ひたすら“経済発展”へと遮二無二邁進する―その無自覚,無知蒙昧,危機意識の欠如―知性の劣化こそ,日本国家・国民のみならず,世界的規模での「内部的,主体的,精神的,社会的諸条件」をめぐる危機の問題なのである。
従って,危機の本質・要因を日本の国家国民の内部的,主体的,精神的な問題に一面化するのは誤りである。
もっとも,「日本の自殺」の著者とて,これまで引用したところから明らかなように,資源問題や環境問題が文明史的危機の具体的顕われであること,即ち「客観的,外部的」諸条件の問題として重要であることは十二分に理解していたと思われる。それでは何故に,このように一面的とさえ思えるほど内部的,主体的,精神的条件の側面を強調したのであろうか。
それは,佐伯教授の論考の次のような指摘から読みとれる。
「明らかに本書は,保守的自由主義というべき立場に立っており,左翼主義,進歩主義に対する批判は痛烈である。戦後民主主義を絶対化した進歩派こそが戦後日本を『自殺』に追い込んだ真犯人だというのであろう。」
このコメントを理解するためには,「日本の自殺」が発表された1975年の日本の政治的・社会的状況を知る必要がある。当時の日本は,美濃部都政をはじめ,いわゆる革新知事が次から次へと誕生し,香山健一氏いわく“福祉のバラまき”による野放図な財政支出が増大し,他方で日本共産党の掲げる「民主連合政府」が今にも実現するかのような社会の雰囲気であった。「日本の自殺」の上記危機意識はそのような時代状況を反映したものであったろう。
しかし,先にも述べたように,「日本の自殺」が掲げたあれこれの「具体的事例」の適否を論ずるのは,ここでの主題ではない。問題の核心は,時代が文明史的転換期(機)を迎えていること,それも「繁栄から滅亡へ」と移ろうとしているという時代認識,危機意識にこそある。そして,それを早や1975年において予言した「日本の自殺」は,その今日的価値をいささかも減ずるところはない。
それを示唆してくれるのが,佐伯教授の冒頭の論考である。以下,その点の紹介に移るが,その前に私の立場を今一度明らかにしておきたい。それは,現下の「日本の危機」,なかんずく「その経済的危機」の本質は何かということについて私の“認識”を明らかにするということである。当然のことながら,それは,それに対する“解”を呈示することも含む。