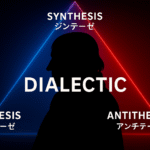1 大きな座標軸で“物を視る”ということ
その座標軸というのは、“時間軸”と“空間軸”の双方である。
ある出来ごとを正しく評価するときに最も大切なことは「大きな座標軸」を手に持って視るということである。
これは私がよく例える話だが、例えば1メートルしか測れないメジャーではせいぜい数十メートルの物体しか測れない。数十キロの長さのものは測れない。それより更に長いものはおよそ測定不能である。これは“空間軸”の問題である。
“時間軸”でも同じことがいえる。数年かせいぜい数十年単位でしか物事を視られない人は、数百年、数千年の単位で動いている物事(事象)の意味を理解することは出来ない。
私が「神々の終焉」(南雲堂・1993年出版の著)で初めて明らかにした「ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、マルクス主義という西洋文明を支えてきた一神教支配の終わり」という観念に辿り着いたいきさつについては、しばらく前に皆様に紹介した「西洋文明の始まりと終わり(私の文明論)」(言論空間2025春号・2025夏号)にその概略を述べている。「水俣病との出会い」に始まるが、最終的にこの観念を決定づけたのは「中東・アラブ世界への旅」であった。
ここで私に働いたインスピレーション(触発)は、時間軸と空間軸の双方にわたる大きな座標軸で全ての物事(世の中の森羅万象)を視るということであった。
時間軸でいえば、中東・アラブ世界こそ今日隆盛を極める西洋文明の発祥の地であり、数千年ないし1万年の歴史を持っているにもかかわらず、私がそこで観たものは、今やバラバラに分解・解体された現実の姿であった。
空間軸でいえば、中東・アラブ世界は今日の世界の全ての矛盾が集中しているといってよい場所であり、何よりも「軍事の問題」を考える上での格好の場所であった。また、我々日本人が「東南アジアないしアジアと日本」という視点から世界を視るのと同じように、「ヨーロッパから視る中東・アラブ」というものが存在していた(たとえば、身近で卑俗な例でいえば、ヨーロッパ=中東を結ぶ飛行便の数や飛行時間など。また、日本ではあまり見ない「ベンツの大型トラック」を中東で見たときなど。大きな問題でいえば、「ヨーロッパにおけるユダヤ人問題とイスラエル・パレスチナ問題」など)。作家小田実氏は、かつて「自分はアメリカに一度も行ったことがないが、アメリカ人よりアメリカがよく分かる」といったそうだが(本当かどうかは分からない。)、私は、やはり、現地へ行くことによって様々な直感が働き、インスピレーションが湧いた。
現代の世界においては、日本でも日本の外でも、このような大きな座標軸で物事を視るということが出来なくなっている。いや、それどころかそれを敢えて拒否し、刹那的に物事を視るというのが主流になっているように思える。
今号では、このことをいくつかの具体例をあげながら考えてみよう。
2 「誰がサダムを育てたか」
これは、アラン・フリードマンという世界的に著名なジャーナリストの著書の邦訳版のタイトルである。邦訳本は1994年にNHK出版から出版されている。もっともこのタイトルは原書のタイトルではなく、邦訳本のタイトルである。
サダムというのは、いうまでもなくあの(第一次)湾岸戦争(1991年)をもたらしたクウェート侵攻により“悪名高き”、“テロ国家の首領”サダム・フセインという元イラク大統領のことである。
この著書の邦訳本には「アメリカ兵器密売の10年」というサブタイトルが付いているように、国際的な兵器密売ネットワークがいかに「サダム」を支援したかが暴露されている。また、「イラン・イラク戦争(1980~1988年)」において、イランのホメイニのイスラム原理主義革命の影響が拡大することを恐れたアメリカがサダム・フセインのイラクをいかに全面支援したかも明らかにされている。
つまり、原題の如何にかかわらず、敢えて俗っぽく要約すると、“あの悪名高きテロ国家の首謀者”サダム・フセインを制御不能なまでに育てたのは、他ならぬアメリカだったということである。そして、手に負えなくなったサダムのイラクをその当のアメリカが懲罰したというわけである。
なお、その後の「9.11」をきっかけとするイラク戦争(2003年)との関連については、スサノオ通信2023年10月12日号外及び、かつてのメルマガ「淳Think」の2003年3月18日号外、4月12日号外を参照されたい。
3 「誰がタリバンを育てたか」
こちらもマイケル・グリフィンという国際ジャーナリストの原著だが、残念ながらこちらも邦訳本(2001年、大月書店)のタイトルである。おそらく、「誰がサダムを育てたか」というタイトルにヒントを得たものではないかと推測している。
この邦訳本は残念ながら少し読みにくい。それはともかくとして、ソ連のアフガン侵攻に抗して闘ったのがムジャヒディン派としてのタリバンであり、2001年の「9.11」の首謀者といわれるサウジアラビア出身のウサーマ・ビン・ラーディンはこの抗ソ連戦争たるアフガン戦争に参戦した。
イスラム原理主義とひとくちでいっても実に様々な潮流があり、たとえばサウジアラビアの国教ともいうべきワッハーブ派はイスラム原理主義のひとつである(たとえば女性の自動車運転免許の取得を2018年まで禁止していたことや、最近まで女性の単独外出を禁じていたなどというのはよく知られているところである。)。タリバンの独特なイスラム原理主義も女性の教育制限など表相的に似ているところはあるが、中東・アラブ世界におけるイスラム原理主義とは異質なものがあるように思われ、アフガニスタン(ないしパキスタン)のパシュトゥン人の部族社会の特質が影響していると思われる。
従って、「誰がタリバンを育てたか」という問いに対し的確な解を見出すのは難しい。しかし、いずれにしろ、ウサーマ・ビン・ラーディン率いるアルカイダの武装をムジャヒディンの一勢力としてアメリカが支援したのは紛れもない事実である。
そして、周知のように、ウサーマ・ビン・ラーディンは、2011年パキスタンのアボッタバードというところでアメリカの特殊部隊により殺害された。私はこのアボッタバードには何度も行っているが、ここは“軍の街”で、ここにウサーマが長年月にわたって潜伏し続けることが出来たというのが不思議でならない。それはともかく、ウサーマ・ビン・ラーディンは死んだが、タリバンは再び“復活”した。アメリカ軍は2021年アフガンから撤退した。アメリカのアフガン戦争というのはいったい何であったのか。
4 因果応報としての「誰が〇〇を育てたか」
因果応報というのは仏教上の用語である。善いにせよ(善因善果)悪いにせよ(悪因悪果)、いかなる結果も“自らが”作るのだという意味である。
「誰がサダムを育てたか」にせよ、「誰がタリバンを育てたか」にせよ、それは、実は“自ら”が生んだものである。“自ら”の中にこそその根拠があるのである。もっとも、多くの日本人は、「サダム」にせよ「タリバン」にせよ、それを育てたのはアメリカであって、我が日本は関係ないというかもしれない。
それでは次のテーマはどうか。
5 「誰が中国を育てたか」
第二次世界大戦後の第二次国共内戦(国民党と共産党の闘い)を経て、周知の如く、中国大陸本土を本拠とする毛沢東主導の中華人民共和国と台湾を本拠とする蔣介石の中華民国が併立した。
この頃の中華人民共和国も中華民国も、ともに“強大な”国ではなかった。そして、1945年に成立した国連において常任理事国の地位を得ていたのは蒋介石政権の中華民国であり、中華人民共和国は何らの地位を有していなかった。
しかし、今や中華人民共和国(以下「中国」と略称)は、地球の隅々にまで影響を及ぼす強大な国家となり、経済的にも軍事的にも押しも押されもせぬ超大国となった。そして、中華民国(以下「台湾」と略称)は、1971年のアルバニア決議により国連の常任理事国どころかその加盟国たる地位すら追われ(表面形式上は脱退)、今や台湾と国交(正式な外交関係)のある国は世界中でたった12の小国のみである。
どうしてこのようなことになったのか。また、それにあたって我が日本はどのような役割を果たしたのか。
1971年のアルバニア決議により台湾政府が国連から追放されるまで、アメリカは“対共産圏封じ込め”政策をとり、台湾は韓国と並んでその重要な最前線を担った。日本もそれに追随していた。しかし、1971年にはキッシンジャーが中国を極秘に訪問し、1972年にはニクソンが電撃的に中国を訪問し、“ニクソンショック”といわれた。ここで180度歴史は方向転換した。ニクソン訪中の7ヵ月後に田中角栄が中国を訪問し、同じ年の内に日中国交回復がなされるとともに、日本と中華民国政府は断交した。
この田中角栄訪中による日中国交回復の決断が、ニクソン訪中によるアメリカの中国承認に追随したものだったのか、それとも日本独自の判断であったかはともかくとして、これを後押しする国内外の2つの流れがあった。
国外では、1964年、フランスのドゴールが中国との国交をいち早く回復した。ヨーロッパと中国の貿易もどんどん進行した。これに象徴される“台湾封じ込め”は次第に国際社会の潮流となっていった。日本国内でも、その頃“日中国交回復運動”が次第に高揚し、中国の広大な市場に魅力を感じた財界の重鎮がこれを加勢した。
私は、後に述べるような個人的な経験から、この中国承認=台湾の孤立化の“世界史の流れ”を創り出した“国際社会”の動機と原因には、蒋介石政権の特質が影響を与えたと思っている。蒋介石政権にせよその後の蔣経国政権にせよ、後述するように、完全な(軍事)独裁政権であり、極めて非民主的な政権であった。当時のアメリカは(即ち米中国交回復以前のアメリカ)は、台湾や韓国の“反共軍事独裁政権”を“対共産圏封じ込め”の世界戦略の“コマ”として利用した。しかしながら、よく考えてみると、このような非民主的な独裁国家は国際社会の支持が得られるはずがない。他方、中国は広大な市場が未開拓であり魅力的に見えた(中国の「改革開放」路線がいつ始まったかは別として、少なくともこのような“国際社会”の中国市場への参入がこれを後押ししたのは事実であろう。)。そういう意味で、その頃、中国は、日本にとっても“国際社会”にとっても“希望の星”であった。
つまり、「誰が中国を育てたか」といえば、それは“我々自身”を含む“国際社会”なのである。そして、我が日本はその中で重要な地位を占めたのである。
6 我々の判断に何が欠けていたか(次号)
7 誰が台湾を見捨てたか(次号)
「政局へのひとこと」
高市総理は、次の通常国会冒頭での衆議院解散を決意したと伝えられている。その動機・原因について色々取り沙汰されているが、私は次のように考える。これは、高市総理を支持するかしないかとは全く別の、私の“直感”である。
私は、自民党総裁選の頃から、高市総理が誕生した場合のある種の“危なっかしさ”を危惧していた。もちろんそれが対中問題ないし台湾問題であったこというまでもない。その危惧は的中した。
そして、今回の国会冒頭解散の報道が正しいとすれば、私は、それはそのような“危うさ”の中で
“高市総理が(先手必勝の)捨て身の勝負に出た”
と判断する。
トランプの“中国接近”にせよ、“世界市場の再々分割=西半球の独占支配”にせよ、予測不能な事態の進展に備えてまずは“足許を固めておこう”ということではないか。
あたっているかどうかは、本人でなければ分からない。