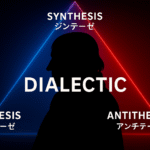論争を避ける国家と
それを容認する国民
―国家・国民衰退への一里塚―
菅総理のジレンマ
菅総理が自らの答弁スタイルで悩んでいる。そのことでいろいろ批判を受けているからだ。いわく―原稿の棒読みである! 目線が下を向いている! いわく―迫力がない!
そのため,最近プロンプター(文字が正面の目線に浮かび上がる機器)を使用し始めたとのこと。このプロンプターは,私の記憶に誤りがなければ,確か細川総理が総理の会見としては最初に使用し始めたと思われる。細川総理の場合は,“リーダーシップを演出する”ための計算づくの小道具だった。しかし,菅総理の場合は“苦肉の策”のように見受けられる。これでは解決にならない。
また,菅総理の答弁は,原稿を言い間違い(読み間違い)したりすることもあった。そのため真意が伝わらず,慌てて訂正する場面もあった。これは,まだ技術的なレベルのことだが,答弁の内容にも批判が及んでいる。いわく―説得力に欠ける! 自らの言葉で語っていない! 総理としてのリーダーシップが感じられない!―などなど。コロナ問題のドイツのメルケル首相の演説と比較され,その違いを嘆く人は多い。
先日の某大新聞の解説によると,菅総理は失言を避けるためか,国会答弁を短く簡潔にし,“安全運転”に徹しているという。しかし,国民がコロナ禍の受難に苦しんでいるときに,果たしてそれでよいのだろうか。“プロンプターの使用”と同じで問題の本質的な解決にはならない。
なぜ,こんなことになったのだろうか。菅総理自身も「こんなはずではなかった!」と思っているに違いない。
菅総理個人の資質やパーソナリティの問題もあるだろうが,問題の核心は,菅総理の8年間(2012年12月26日から2020年9月16日まで)にわたる官房長官時代に作り上げた(作り上げてしまった)答弁スタイルそのものにその最大にして根源的な要因があるということだ。
安倍政権下で長期にわたって官房長官をつとめた菅総理の「官房長官記者会見」のスタイルは,事前に記者側から質問書を提出させ,それに対する“答えを読み上げる”というものであった。また,全体として記者からの追及や議論の応酬を避けるための様々な技術的・物理的制約があったという。
しかし,そのことに負けず劣らず深刻なことは,菅総理の官房長官時代の答弁では,次のようなセリフが多用されたことにある。
「お答えを差し控える」
「答弁を差し控えたい」
「お答えする立場にない」
「説明を差し控えさせていただく」
このような“決めゼリフ”を用いないまでも,様々な表現を用いて聞かれたことに直接に答えない場面が極めて多かった。このことは,マスコミを通じて多少は伝えられていたが,私はあるルートにより極めて嘆かわしい事態として伝え聞いた。
このような答弁スタイルは,一部の政治家や評論家には,“守りに強い”,“実務能力のすぐれた”政治家の答弁として高く評価された。
しかし,このような答弁スタイルは,結局のところ「異論」「反論」を封じ,論争を避けるものに他ならず,“無気力”や“諦め”を助長・蔓延させるだけであり,国家・国民のためにならない。多種多様な事実factを証拠evidenceをもって摘示し,異なる観点から激しく論争を展開させることによってはじめて真相が浮かび上がり,また,より良い解決方法が見出される。
国民の運命を決める国政の場にあってこそ,そのような激論が闘わされることが求められる。
“逃げる”“はぐらかす”“封ずる”“押さえつける”―このようなことばかり行っていると,国家や社会は活力を失って間違いなく衰退する。
そして,皮肉なことに,菅総理が長い官房長官時代に作り上げたこのような答弁スタイルこそが,今まさに菅総理を苦しめている。人間,いったん身に付けた習慣や習性からは簡単に抜け出せない。守りに徹し,“黒衣(黒子)”に徹し,ひたすら「論争」「議論」を避けてきたスタイルが,―国の宰相―総理大臣の答弁として通じるはずもなければ,許容されるはずもない。ましてや,コロナ禍という未曽有の事態に直面する一国の総理として,どのような政策を立ち上げ,それを国民に向かってどのように“発信”するのかが問われているのである。今の菅総理の直面するジレンマは,極めて深刻にして本質的な問題である。
ところで,このような菅総理の官房長官時代の答弁スタイルを許容・助長してきたのは,官邸の記者会(内閣記者会,通称官邸記者クラブ)である。一部の記者たちはこれに抵抗してきたが,大勢はこれを許容してきた。それだけではなく,ときにはこれに迎合さえしてきた。
安倍前総理の記者会見を含め,官邸の記者会見のこのような異様さが広く国民に知られることとなったのは,5問のみで質問を打ち切られた安倍前総理の記者会見で
「まだ質問があります!」
と何度も何度も叫ぶフリージャーナリストの江川紹子さんの姿がSNSを通じて広く拡散されてからだった。
全てのマスコミ記者がそうだとはもちろんいわないが,日本独特の「記者クラブ」システムの中で,日本の大手マスコミは,このような異様な官邸記者会見のあり方を許容し,更には助長してきた。
かくては,日本の国家は確実に衰退する。
次に,私自身が最近直接体験した日本の大手マスコミの問題点をお話する。
子(霞が関の官僚)は親(国のトップリーダー)の背中を見て育つ
マスコミ問題の個人的体験の話に移る前に,菅総理のこのような答弁スタイルの弊が広く霞が関官僚の間に“伝染”し,蔓延しているのではないかという危惧について,まずお話しておきたい。
場所は,霞が関の金融庁の一室である。ときは2020年(令和2年)12月某日の午後のことである。
私は,昨春から,金融商品取引法(旧証券取引法)に基く「課徴金審判事件」を担当している。“仮装売買”や“インサイダー取引”があったということで,私の依頼者に巨額の課徴金が課せられようとしている事件である。課徴金制度それ自体は独占禁止法にも存在するが,金融商品取引法の場合は,“仮装取引”等の不正な証券取引等があった場合に,犯則事件として刑事罰が課せられる手続と,課徴金審判事件として行政処分が課せられるという手続の,2つの手続に途が開かれている仕組みとなっている。
そのため,課徴金審判事件(の手続)は,一方で「民事事件」のようでもあり,他方で「刑事事件」のようでもある。異質な手続が合体する誠に奇妙なものであり,まるで「ぬえ」(鳥とも動物ともつかぬ得体の知れない想像上の生き物)のような存在である。
そのため,巨額の課徴金が課せられようとしているこのような案件を解決するためには,熟練した民事・ビジネスロイヤーとしての経験・能力と,大型刑事事件を経験したことによる刑事弁護能力が,併わせ求められる。
たとえば,ビジネスロイヤーとして,証券取引(株取引)の知識はもちろんのことだが,TOB(「株式の公開買付」)の仕組みやTOBの仕掛けられる背景なども理解しておかなければならない。また,株価がどのように算定され,或いは決定されるかの知識を有しておかなければならない。他方で,課徴金審判事件は「犯則事件」ではない,即ち「刑事事件」として取り扱われてはいないというのに,証券取引等監視委員会による苛酷な“取り調べ”が行われる。そこで作成された「質問調書」というタイトルの書面は,刑事事件の「自白調書」とまるで変わらない。その「信用性」はもちろん,「任意性」も問題となる。
そういう意味では,若い頃から大型の冤罪(刑事)事件を担当し,たくさんの大型刑事事件を受任した経験がある一方,民事・ビジネスロイヤーとして長年にわたる経験を積み重ねてきた私にとっては,この巨額の課徴金審判事件は,うってつけの案件であった。冤罪事件においてどのようにして「虚偽の自白調書」が作られるかを,とことん知り尽くしているからである(このことは,また別の機会にご説明しようと思う。)。
ちなみに,この事件を受任してから,例の江川紹子さんが,金融商品取引法の「課徴金制度は刑事事件以上に冤罪を生みやすい」と批判していることを知った。さもありなんと思う。刑事事件では不当な“冤罪”でもあるにもかかわらず,有罪とされ,懲役刑に服役した人さえいるが,課徴金審判事件でも,同じように“泣き寝入り”している人はいないだろうか。懸念している。
この事件でも,依頼者があやうく“虚偽の自白調書(質問調書)”をとられそうになった。頑張ってかろうじて踏みとどまった。だが,参考人ともいうべき関係者の「自白調書」は作成されてしまっており,これは「虚偽自白調書」ではないかとの確信をもっている。
このように,金融商品取引法の課徴金審判事件は,調査(捜査)段階では,極めて「職権主義的」でいわば刑事事件的色彩が濃いが,ひとたび「審判」手続が開始されると,ガラリと変わって一般の民事事件手続と変わらなくなる。証拠の提出や採用にあたって,刑事事件のような様々な制約がなく,良くも悪くも自由にこれを行うことが出来る。
そして,民事の口頭弁論期日の前に行われる「弁論準備手続」のような「準備手続」を通じて「争点整理」が行われる(刑事事件でも近時は「公判前整理手続」というのがあるが)。
さて,前置きが長くなったが,私が問題を感じたのは,この課徴金審判事件における「準備手続」(非公開)における金融庁職員の発言である。
当方は,この準備手続の少し前に,詳細な主張書面を提出し,当方の見解を全面展開した。それとともに関係人の「虚偽自白」を撤回する「陳述書」を含む多数の証拠を提出した。
そこで,これに対する金融庁の「指定職員」(手続上このように呼ぶ)の再反論をいつまでに提出するかが問題となった。これに対する金融庁の指定職員の回答は,私の予測したよりはるかに先の期限であったので,すかさず私は
「もっと早く出せないのか」
「あなた方は審判手続開始前に,数か月にわたり,しかも連日,関係者を取調べているではないか」
「今更何を調べるのだ」
と追及した。
それに対する金融庁の指定職員の回答が,驚くべきものだった。いわく,
「そんなことをあなた方に説明する必要はない」
これがなんとまあ! 菅総理(官房長官)の答弁にそっくりだったのだ!
私は,この答弁にショックを受けた。なぜなら,この職員のそれは,“計算づく”の答弁というより,その場で“思わず出してしまった答弁”と感じられたからである。
いわば,菅総理(官房長官)の“口ぐせ”というべきものが,いつの間にやら霞が関(官僚)の間に蔓延しているのではないか!? それはそれで大変恐ろしいことである。そんな恐怖を感じたのである。
そして,最近霞が関官僚の話を聞いたところによると,皆,「あれで(菅総理の答弁スタイルで)済むならありがたい!」と思っているようだ。金融庁職員の“とっさの反応”は決して例外ではないのである。
東京地検特捜部の“広報室”(“人民日報!?”)と化す日本の大手マスコミ
私は,マスコミには親しくしている友人・知人も多く,日本のマスコミには常々“頑張ってもらいたい” と思っている。マスコミを敵視しているわけではない。
しかし,私が最近久しぶりに体験した日本のマスコミの報道姿勢は,かつてのそれとは様変わりしていた。極端というか,とにかくひどい,ひど過ぎるのである。
読者や視聴者に論争の場を提供をしない! 臭いものに蓋(ふた)をする! こんなことが我が国社会のあらゆる場面で進行しているのではないか,と痛感させられた。
分量が長くなったので,このことは次号に譲る。