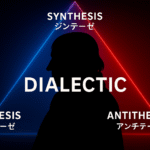3 私と検察,検察と政治(その2)
―水俣病自主交渉川本裁判―
(1)秦野章元法務大臣との出逢いを創ったもの
人生の禍福(かふく)は糾(あざな)える縄(なわ)の如し―という。
人生の出逢いが織りなすのは,縦糸と横糸がつむぎ出す絶妙な綾(あや)というべきか。
前号で紹介した秦野章元法務大臣と私との出逢いのきっかけを作ったのは,「水俣病自主交渉川本裁判」で私が「公訴権濫用による公訴棄却判決」という“歴史的判決”を勝ち取った4名の弁護団の一員だったということである。しかも,私は,その“歴史的判決”を勝ち取るための刑事訴訟法理論を構築する弁護団の中の主柱だったからである。
通常,刑事訴訟(刑事裁判)では,被告人として起訴されれば,裁判所は「有罪か無罪か」を審理し,法廷に提出された証拠に基いてそのどちらかを「判決」として判断する。しかし,私達弁護団は,そのような“常識的な枠組み”自体を超越した判断を裁判所に求めた。
(2)「水俣病自主交渉川本裁判」とは
「水俣病自主交渉川本裁判」というのは,水俣病患者でありその運動のリーダーであった今は亡き川本輝夫氏が,多数の患者・家族や支援者らとともに丸の内にあるチッソの東京本社に補償や社長の謝罪を求めて交渉に出向いた過程で発生した“事件”に端を発する。この自主交渉要求は長期間にわたって続けられ,患者・家族・支援者らは本社前の路上にテントを張って寝泊りし,長期戦を闘った。
チッソ側は,多数の従業員によるピケを張り,これを阻止しようとして川本輝夫氏らともみ合いになった。そのもみ合いの際に,川本輝夫氏がチッソ従業員に“暴行” を働き“傷害”を負わせたということで,5つの“罪体”が起訴された。それが「水俣病自主交渉川本裁判」であった。もっとも“傷害”といっても,せいぜい全治1週間ないし2週間程度の軽微なものであったが。
通常であれば,川本輝夫氏は“有罪”となるはずである。せいぜい「可罰的違法性なし」「行為に違法性なし」として“無罪”となるのが精一杯であろう(ここでは,難しい刑法理論や刑事訴訟の解説は省く。)。
しかし,私たちにとって,“有罪判決”はもちろん,たとえ“無罪判決”であっても到底承服出来ないものであった。
(3)“巨悪”を見逃す検察
なぜなら,何十万人もの水俣病患者を作り出し,その裾野には数百万人に及ぶ膨大な数の健康被害を作り出したチッソの“巨大な犯罪”(殺人・傷害の罪)が全く捜査・起訴されず検察によって放置されているというのに,なぜやむにやまれぬ被害民の行動の些細な結果を捉えて,“即時,苛烈な”処罰を加えようとするのか。それは絶対的不正義ではないのか。「巨悪を眠らせない」「巨悪を処罰する」というのが“検察の正義”なら,なぜチッソの重大犯罪を放置するのか。
(4)「公訴権濫用による公訴棄却判決」を求める
“無罪判決”なんてとんでもない! それは検察官の川本輝夫氏への起訴がとりもなおさず合法・適法であることを認めることにほかならない。起訴自体が許し難い,起訴自体が違法である―それが私たち弁護団の主張であり,闘い方であった。
それが,川本輝夫氏に対する起訴は「公訴権の濫用」により違法・無効であるから「公訴棄却の判決を求める」というものであった。従来から「公訴権の濫用による公訴棄却判決」の可能性を主張する学説は多数あり,論文も膨大な数に及んでいた。刑事裁判の実務の判決でも,その「理論的可能性」を指摘する判例もそこそこにあった。しかし,現実の刑事裁判でこれを実際に認めたものは皆無であった(注―この点厳密にいうと若干のコメントが必要だが,ここでは省く。)。
案の定,第1審の東京地裁の判決は,“有罪判決”を下すとともに,その「量刑」については,
「検察官の懲役1年6月の求刑」
に対し,
「罰金5万円,執行猶予1年」
という“驚くべき(軽い)”判決であった。このように極端に軽い「量刑」にしたのは,この事件の“重み”に対する担当裁判官の“苦渋の判断”であったと思われる。しかし,これは“無罪”どころか,明確に“有罪判決”である。
私たちは,即日控訴した。併せて,その日,その場で東京地検に出向き,“歴代のチッソ幹部を殺人・傷害で告訴する”という告訴を口頭で行った(この点は,あとで述べる。)。
「公訴権濫用による公訴棄却判決」の理論構築を担当した私は,控訴審でどのように闘うべきか,日夜呻吟した。この点に関する日本の学説・判例は余すところなく全て読んだ。何度も何度も繰り返し読んだ。しかし,なかなか控訴審の裁判所を最終的に説得する決定的な理論構築が出来なかった。挙句の果ては,神田の古本屋に出向き,カタカナと漢字で書かれた古びた戦前の「公訴理論」の書籍まで手にして研究した。しかし,益々“袋小路”に入るだけだった。
そんな中,法律時報という雑誌に松本時夫裁判官が書かれた論文のひとつの脚注に眼がとまった。それは,アメリカ合衆国における憲法修正14条の平等条項に反するような“不平等な起訴”discriminatory prosecutionについて書かれたColumbia Law Reviewの論文だった。それまで何度も読み返した松本時夫判事の論文だったが,このときなぜか急にこのColumbia Law Reviewの記事の“原典”そのものにあたってみようという気になったのだ。
それは“目からウロコ”の論文だった。その論文にはどうしたら差別的訴追discriminatory prosecutionとなるのかという「立証」について延々と書かれていたのだった。それまで私が格闘してきた日本の刑事訴訟法学の論文・成果は余りに“概念法学”的(観念的・抽象的)なものであった。「立証」について触れたものは皆無といってよかった。
そして,私たち弁護団は,すでに控訴審において,一方でチッソの水俣病犯罪を訴追しようと思えば戦前においてさえ出来たはずという法律の歴史を振り返って立証しており,他方で患者や漁民,支援者らのやむにやまれぬ行動や些細な行動がことごとく刑事訴追され有罪になった歴史を具体的に立証していた。すでに我が弁護団は,Columbia Law Reviewのいうような立証を,しかもその「日本版」を実践していたのである。ちなみに,そのことの示唆を与えてくれたのは,田尻宗昭氏という海上保安庁の保安官が,「四日市・死の海と闘う」という本で紹介していた苦闘の物語であった。法律がないから処罰出来ない―という逃げ口上を許さず,「既存の法律を駆使して,海を汚す公害企業の刑事責任を追及出来る」という信念に基く闘いの歴史がそこで切々と語られていた。
私の心は“台風一過の青空”のように晴れ渡り,「公訴権濫用による公訴棄却判決」を勝ち取るための理論的アイデアが,次から次へ泉の如く湧いてきた。あとは,Columbia Law Reviewにヒントを得たこの新しい理論と伝統的な刑事訴訟法理論の成果との間に“架け橋”をかけるだけである。
私たちは(少なくとも私は),控訴審での“勝利”を確信した。
(5)東京高裁で歴史的判決を獲得
東京高裁は,私たちの控訴を受けいれ,東京地裁の1審判決(有罪判決)を破棄し,「公訴権濫用による公訴棄却判決」を言い渡した。素晴らしい内容の判決だった。
驚愕した検察は,その日の内に東京高検,最高検の内部決裁を瞬時に取り付け,即日,上告した。
これを,当時のマスコミは“異例のスピード上告”として批判した(このことも後述する。)。
ところで,この「公訴棄却判決」に対する,いわゆるリベラル派・人権派の弁護士の反応は複雑だった。私の恩師のひとりである古賀正義弁護士は,古賀事務所の弁護士全員同席のうえ,祝宴を被いてくれた。そして,こうおっしゃってくれた。「錦織くん,これがアメリカなら,あなたの事務所は門前市をなすだろう。」――と。
しかし,別のあるリベラル派弁護士はこういった。
「あれは,裁判長(寺尾裁判長)がよかったから。運が良くてたまたま勝っただけ。最高裁で必ずひっくり返る」
また,当時私は故杉本昌純弁護士の主宰する刑事判例研究会に所属しており,この判決をレポートした。すると,あるリベラル派弁護士からこう言われた。
「何だ,この判決は!これは“革命は無罪”といっているようなものではないか!」
と揶揄された。それに対し,私はその場ですかさず反論した。
「もしあなたが本当に“革命は無罪だ”と信ずるのであれば,それを“立証”してください。私たちは“公訴権の濫用”を裏付ける事実を“立証”しました。」
その時主宰者である杉本昌純弁護士は,
「そうだ!錦織君たちは立証に成功したのだよ!」
と言って手をたたいて私の反論に加勢してくれた。
その時私は心に誓った。
「よし,それでは最高裁でも勝ってみせよう。それなら文句がなかろう。」
(6)最高裁は検察の上告を棄却
上告審では,さらに理論武装に磨きをかけた。特に,刑事訴訟法と憲法理論との関係を重視したり,また,ドイツの「起訴法定主義」との比較法的考察まで行った。
ただ,心がけたのは,従来の伝統的理論との“架け橋”を架けることに最大限腐心し,更に過去の多数の最高裁判例の分析を行い,それとの整合性を力説した。その結果,絶対に負けないとの確信を深めた。
私の確信どおり,最高裁は検察の上告を棄却した。「公訴棄却による公訴棄却判判決」はここに「確定」したのである。
ただ,勝つには勝った(東京高裁の「公訴棄却判決」は「確定」した。)ものの,最高裁の判決理由は,読むにたえないものであった,支離滅裂といってよい。この判決を評してある著名な検察官は「我々は相撲に勝って勝負に負けた」といった。
最高裁が「政治裁判所」たることを改めて思い知らされた判決であった。私はこれを機に「日本の刑事司法に未来はない」と思うようになった。
(7)水俣病が私に教えてくれたもの
水俣病患者が私に教えてくれたものは,極めて根源的なことである。
水俣病患者がいかなる存在であり,或いはあったか―その一端は先ほど亡くなられた石牟礼道子さんの「苦海浄土」に余すところなく表現されている。「苦海」と「浄土」という根本的な矛盾が患者達の中でどのように“同居”していたかが独特のタッチで表現されている。
水俣病患者は心優しき人々である。塗炭(とたん)の苦しみを味わっているにもかかわらず,チッソの幹部たちと互いに人間として向き合おうとする。
私自身は,このように受けとめている。
「水俣病の患者さん達は,自らの身体を犠牲にしながら,“明日の私たち”,“人類の未来”を予測し,警鐘を乱打してくれている人々である。」
水俣病患者の数は,日本全体,或いは人類全体からみれば(相対的に)少数かもしれない。しかし,水俣病患者は,自らの身体や命を犠牲にしながら,私たち日本人全体,人類全体に対し,「このような惨禍(さんか)を放置しておくと,やがて日本人全体,人類全体に大きな災いが振りかかる」と警告してくれているのである。
“公害列島”といわれた日本でも,いつの間にか「公害」という言葉は使われなくなり,「環境問題」という言葉に置き換えられた。それは,この問題が,一握りの被害民の問題ではなく,人類共通の問題として理解されるようになったことを意味する。しかし,他方で,「いったい誰が環境を破壊しているか」についての認識が甘くなってしまった。
私がもうひとつ感じたことがある。それは水俣病患者が闘わなければならなかったのは,決して「チッソ」やそれをかばう「行政」のみではなかったということである。
それは,水俣の地域住民の心ない感情,差別感情や言動であった。「奇病,伝染病」として近隣の人が鼻をつまんで患者のいる集落を通りすがる。
私は,この事件を通じて思い当たることがあった。それは,そのような地域社会の“いびつな”“負の感情”が古い日本の地域社会のどこにでも残っていることを知っていたからである。なぜなら,それは私が18歳で上京するまで育った古い古い歴史的重みのある地域社会独特のものだったからである。私が育った日本の伝統的・閉鎖的地域社会と水俣病患者を苦しめたものは全く同質のものであった。そして,実は,日本のどこにでもあるものだった。
これはおそらく,江戸封建時代に,日本の“村社会”につくりあげられたものであると思われる。
それを理解していただくためには,黒澤明監督の歴史的名画「七人の侍」をみていただくとよい。
(8)水俣病患者が私に教えてくれた3つの教訓
私個人として,教訓を与えられたものが3つある。
ひとつは,
「海は広いな,大きいな」
というのは間違いだということである。海は有限であり,地球は有限だということである。
当時,海は無限であり,有毒な工場廃液(水銀)を流しても,“希釈”される(薄められて無害化する)と考えられていた。
しかし,植物性プランクトンに始まる「食物連鎖」の中で,動物性プランクトンから大きな魚に至り,最後に人間がこれを食するまでの過程で,水銀の濃度が次第に濃くなっていく(薄められるのではない!)ということがわかった。最後に人間が魚貝類を食べるときは,水銀濃度は極めて高くなっていたのだ。
今日,「地球は有限である」「資源も有限である」ということが常識となっている。しかし,私たちは忘れてはならない。そこに至るまでには多大な犠牲が払われたということを!
また,水俣病は,それまでの医学の常識を覆した。当時,胎児性水俣病の子供を産んだ母親たちはこういっていた。
「お腹の中の子供が私の毒を全部吸い取ってくれた」
「だから,胎児性患者の母親の水銀中毒の症状は軽くなる」
これに対し,「そんな馬鹿なことはない」「むしろ胎児は母親のお腹の中で守られている」というのが医学の常識だった。
しかし,母親たちのこの思いは,その後医学的にも正しいことが立証された。“生命の不思議”を思わざるを得ないとともに,このことから私たちの学ぶべき教訓が沢山ある。
また,水銀は高価である。そんなものを海に流すものはいないとか,無機水銀が有機化することはあり得ない―それが専門家の常識だった。それもまた打ち破られた。
相当に長くなってしまったので,この問題を通じての「私と検察,検察と政治」や「私とマスコミ」については次号以降に展開させていただくこととする。